主な掲載記事
- 読売新聞
- 2004年4月16日掲載
- 京都新聞 山城版
- 2003年9月13日掲載
- 京都府中小企業総合センター
- ホームページ掲載記事
読売新聞 2004.1.6掲載
元気出せ関西ー元気印特注に応じ技術向上
シネマ工房
奥村恵一社長(56)が約30年間勤めた映写用スクリーン業界の最大手を辞め、身内ばかり5人で起業した。
副社長は、妻の雅子さんだ。
手がけるのは、液晶プロジェクターやOHPの映像などを映すスクリーンだ。主に、会議室や教室で使われるが、
既製品のサイズが合わないこともある。細かい注文に応じることで、業績を伸ばし、業界3位にまで成長した。
奥村社長は「特注を避けるところも多いが、一つ一つがノウハウの蓄積になる。逃げたらおしまいと踏ん張るうちに、
技術力も高まった」と振り返る。
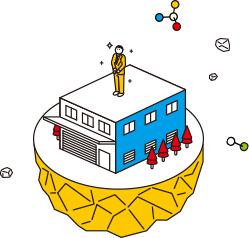
商品の善しあしは、反射効率で決まる。微粒のパールエッセンスを表面加工したり、
光学レンズのガラス球を表面にちりばめたりと、工夫を凝らす。
スクリーンは、普段は収納しておくため、巻き上げる技術も必要だ。遠心力で上下させるタイプが主流だが、特許の「ロータリーストップ機構」では、静かで緩やかな動きを実現し、スクリーンの痛みも減らした。
社名の「工房」は、「数をこなすより、モノづくりに徹する」という決意の表れだ。
ただ「シネマ」と銘打つも、映画館向けは手がけていない。「最近は、ホームシアター向けの注文もある。うちのスクリーンで映画を楽しむ家庭が増えると、うれしい」と映画好きの素顔をのぞかせた。
京都新聞 山城版 2003.9.13掲載
元気です 人・店・企業
映写用スクリーン製造 シネマ工房(八幡市)
ー簡単操作の独自技術 少量多品種にも対応ー
ちょっとした表情で見せる感情の機敏、大迫力の爆発シーン、コンピュータグラフィクスにより作り出された宇宙空間…。
最新技術に工夫や苦労を重ねた映像も、美しく映し出すスクリーンあってこそだ。
「シネマ工房」は、会社での会議や学校での教材、舞台装置などで利用するスクリーンを製造する。生地の裁断や縫製など
工程の多くが手作業で、社名の「工房」の由来でもある。
同社は、大阪のスクリーン製造会社に三十年近く勤めていた奥村恵一社長(56)が1992年に枚方市で独立して設立、
96年八幡市の上津屋工業団地内に移転した。

従業員は五人で出発したが、長引く不景気の中で順調に業績を伸ばしてきた。現在、業界内三位の国内シェアを誇り、従業員も三十人を超える。
「少量他品種で、ていねいな商品を作ってきた。リスクがあるものも引き受け、さまざまな要求、細かいクレームにもきちんと対応してきました」と奥村社長は話す。「映像を欲しがっていれば、しんどくても手をかけて提供したいですから」独自技術にも自信を見せる。
従来型の天吊式スクリーンでは、停止と解除にコツが必要で、巻き戻すときに勢いがつき、スクリーンの耐久性に課題があった。
同社の製品は特許の「ロータリーストップ機構」という、スピードや力に関係なく、簡単に操作できる機構を備える。業界では先進的な米国でもできていない技術だという。
京都府中小企業総合センター ホームページ掲載記事
我が町の企業紹介 ~京都府 北から南から~
株式会社 シネマ工房
京都と大阪の中間に位置し、石清水八幡宮や松花堂などの歴史・文化資源を有し、第二京阪道路の開通・京都第二外環状道路の開通予定など、交通拠点として注目される八幡市の上津屋工業団地。ここで映写用スクリーンを製造されている株式会社シネマ工房の奥村恵一社長をお訪ねしました。多品種少量生産を強みに全国展開されています。
スクリーン製造業界に40年
大阪にあるオーエスという叔父がやっていた会社に創立当時から30年近く勤めていました。経営方針などが変わったのがきっかけで、退職したのが13年前です。
それから半年ほどして会社を立ち上げました。創業するといっても業務内容は元勤めていた会社がスクリーン製造メーカーでしたので同じ業務です。やっぱり自分が長い間やってきたことしかできないと痛感して他に選択肢がありませんでした。
平成4年に身内ばかり、5人で始めました。バブルがはじけて不景気の中、よくここまでやってこられたと思います。ですから前の会社とこの会社の10年ほどと合わせて40数年スクリーン製造業界にいることになります。
現在は国内シェア業界第3位です。取引先は主に会議室、講義室の設備である黒板や映像関係を扱う会社です。
上津屋工業団地で新たな出発
創業当初は50坪ほどの枚方の貸工場からスタートしました。この地に移ったのは平成8年です。当時私が土地を探しているのを知っていた仕入先の工具屋さんが教えてくれました。
お墓が横にあるので最初は迷いましたが、商売には縁起がよいと聞きここに決めました。
創業当時は私が製造から営業まで何もかもやっていました。特殊な業界ですので資金があっても材料が買えるとは限らないんです。その点、前の会社でも各部門に携わっていましたから業者との信頼関係もあったし、この道に長くいた経験が活かされました。
独自の技術へのこだわり
当社の業績が伸びたのは、大手では引き受けないリスクのあるものや、細かい注文に対応してきたからだと思います。
オリジナルの技術を追求して、失敗してもやり直したらよい、という考えのもとに何でも積極的に取り組んできました。
その一つひとつがノウハウの蓄積になります。逃げたらおしまいと思っています。これが当社の基本理念です。
商品構成は徹底的な少量多品種で、例えば20mほどの大スクリーンを作っている横で小型のものを作るという状態で、
同じものを多くつくることはありません。間口は広く、数量よりもきめの細かい丁寧なものづくりをすることが、
「工房」という名前をつけたこだわりです。

平成4年に会社を設立以来、関西、東京を中心に大学、ホテル、企業など260以上の大会場のスクリーンを手がけてきました。
最近は講堂や会議室だけでなく、ビアガーデンなど多くの人が集まる所にスクリーンを設置するなど、様々な場面で需要が増えています。
プラズマテレビの普及も気になりますが、大会場にはスクリーンが必要だと思います。特に当社は特注が得意ですし、また、液晶プロジェクターを使ったプレゼンテーションの需要も広がってきています。
天吊型のスクリーンの場合、従来の遠心力を使ったツメ式では停止と解除にコツがいります。当社の製品は、ひっぱったり戻すときの力やスピードに関係なく停止と解除ができます。
日本では当社と(株)オーエスだけが作っています。構造的には簡単なようで非常に難しく、
スクリーンの両端についているロータリーストップ機構は、プラスチックに特殊な溝を掘って、その中に直径1mm程度の粒子を泳がすことに
よって、微妙な力の調整をしています。この部分が大きなポイントで特許をとっています。中国もアメリカも
これができていません。例えばアメリカなら、ユーザーが加減して操作してほしい、という考え方です。
日本ではそういうものは商品として通用しないし、細かいニーズに応えることで、新しい使いやすい商品が生まれます。
また、生地メーカーと共同で環境に優しいスクリーンの開発や、カラー鋼板の収納ケース、再生可能なアルミ天板を採用しています。
価格、耐久性などでまだまだ改善の余地がたくさんありますが、メーカーとして新しく取り組んでいかなければならない課題だと思っています。
これからも着実に一歩ずつ
これからも地道に長くやっていけたらというのが正直なところです。一定の評価を受けてユーザーのニーズに応えた商品を提供していければ
それ以上の欲はありません。ただ社員への責任は大きいですから、とにかく会社の継続が先決です。
ここ八幡はあまり大きく変わらないのが魅力です。昔からの風情があってよいと思います。
ただ交通面では第二京阪道路に加えて高速道路が久御山町から大山崎町につながり便利になりましたので、この場所は本当に
よかったと思います。私用では通勤が大変便利になりましたし、物流面でもこれから効果がでてくると思います。





